2019年7月吉日、に鹿児島でスタートした「鹿児島離島文化経済圏(通称:リトラボ)」(離島地域おこし団体連携支援事業)の後半レポート(#01はこちらから)。プロジェクトを牽引する上甑島の山下賢太さんの挨拶につづき、開催されたプレゼンテーションとワークショップの模様をお届けする。
(写真・鹿児島離島文化経済圏 文・鯨本あつこ)
この日、鹿児島市のクリエイティブ産業創出拠点施設「mark MEIZAN(マークメイザン)」に集った参加者は85名。その半数が鹿児島の島から自費で駆けつけていた。
鹿児島県の離島地域おこし団体連携支援事業として、「鹿児島離島文化経済圏(リトラボ)」や「セイルミーティング」を企画した、上甑島(かみこしきじま)の山下賢太さんのプレゼンを聴講した参加者は、島を支える「同士」に出会えるかもしれない期待を膨らませているようだった。(詳しくは#01へ)
ここで、鹿児島離島を支える人々に向けた基調講演がスタート。まずは、鹿児島最大の島・奄美大島(あまみおおしま)南部の瀬戸内町でクラフトビールをつくる、合同会社奄美はなはなエール代表の泰山祐一さんが、プレゼンを始めた。

「最大の危機は目標が高すぎること」
泰山さんは神奈川県生まれ。祖父が暮らす奄美大島に帰省する度に、島の役に立てることはないかと考え、瀬戸内町の地域おこし協力隊に応募。協力隊の任期終了後に、奄美はなはなエールを立ち上げた。
奄美大島にはかつてビール製造を行う黒糖焼酎蔵もあっていたが、近年は地ビール製造が行われていなかった。
そこで泰山さんは「地元のものがはいっているビールで乾杯できたら面白いのでは?」と考え「自分の事業を元気に、地域の事業も元気にしていきたい」という思いを胸に、地ビール開発に着手した。

0から1をつくるには、産みの苦しみも付いてくる。「『うまくいくの?』『成功するの?』とよく言われ、自分のなかでも葛藤はありました」と泰山さんは語り、最終的には「自分がどう地域に貢献していくのか?」を考え「自分がやっていける場所でやりたいことをやろう」と、方針を定めた。
奄美はなはなエールには、奄美大島特産のたんかんやパッションフルーツ、黒糖が使われているが、泰山さんは地元農家とコミュニケーションを続けるなか「地元の農家は加工品だけを使ってもらうことは求めていない」ことに気づき、原材料としての取引だけでなく、農産物の営業も手伝い始めたという。

そんな泰山さんが展望する、今後の事業規模は「自分がやっていけるくらい」。事業における最大の危機を「目標が高すぎること」と表現し、「地元に必要とされる存在であり続けられること」を念頭にする活動方針が、会場の参加者に共有された。
参加者の中には同じく島に移住し、産品の製造販売を手がける人も多い。同じ鹿児島の島で「地元に宝をつくる」ために活動する同士の想いに、深く頷く姿が見られた。
「グローバルの対義語はローカルではなく、コミュニティ」
鹿児島離島で生きる当事者のプレゼンテーションに続き、セイルミーティングに「多角的な視点」を吹き込むべく登壇したのは、東京で生まれ育ち、日本とイタリアの二拠点生活をするプロジェクトプロデューサーの古田秘馬さんだ。

これまでに古田さんが手掛けてきた東京の農家レストラン「六本木農園」では、喜界島(きかいじま)の農産物をはじめ島々の食材も多く扱い、丸の内エリアのOLやビジネスマンが集う「丸の内朝大学」では、奄美大島の「シマ唄クラス」を複数回開催。受講生が島を訪れるフィールドワークを通じて、島と島ファンのつながりをつくってきた。
そんな古田さんが参加者に向けて、まず語りかけたのは「グローバルの対義語はローカルではなく、コミュニティ」であることだ。
たとえば、グローバルとローカルの対比では、数の多さによって商品を安くできるなどの経済性が指標となり、ローカルが割高になってしまう。しかし、その対義語がコミュニティになると、その常識が変化する。
「たとえば不動産価値で考えると、海辺の物件は価値がありません。でも、サーファーにとってはものすごく価値がある。僕たち(=島)はマイノリティだが、誰に対しての価値観なのかを問えば、世の中につながっていけるんです」(古田さん)。

インターネットが発達し、個人が世界とつながれる時代となった今、テレビ番組は動画サイトに、百貨店はアマゾンやメルカリに、銀行はクラウドファンディングや仮想通貨にと、変化が起こっている。この状況を「社会がコミュニティ側に寄ってきている」と表現する古田さんは、リトラボの参加者に、新しい時代の仕組みをつくることを提案する。
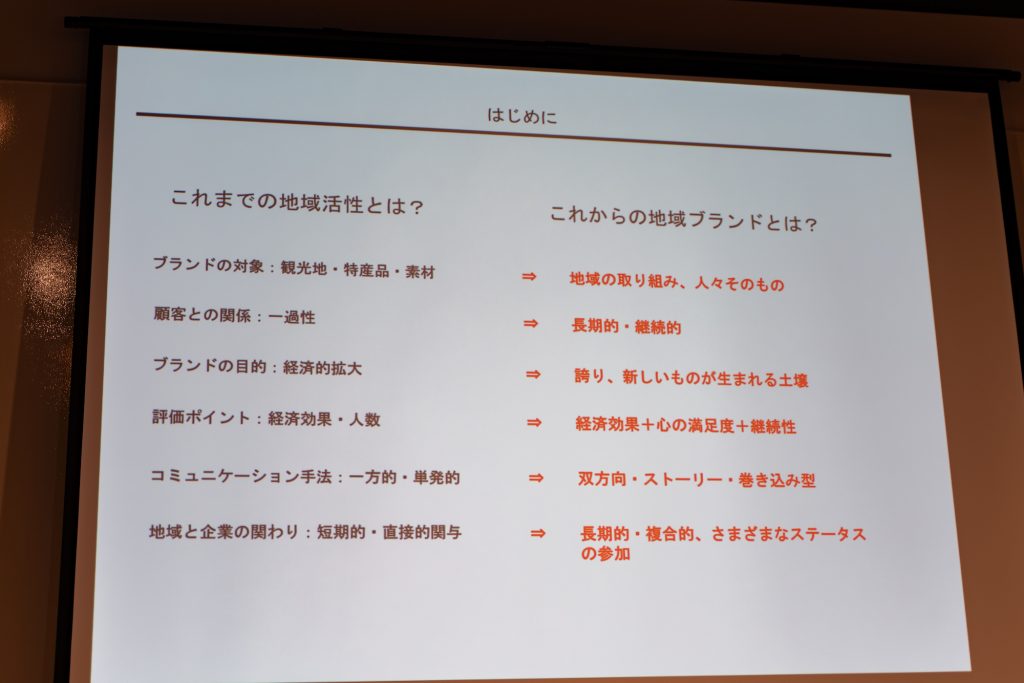
「ここで大事になるのは『高付加価値』ではなく『他付加価値』です。高付加価値には限界があり、どれだけ良いりんごジュースでも1本1万円では売れません。では、どう違う価値に変えるのか?」(古田さん)
古田さんは自身がプロデュースを手がけた香川県の「うどん」を例に話を進める。庶民の味として親しまれているうどんは、最高級の小麦粉をつかっても1玉1,000円で販売するのは難しい。しかし、「香川県民はうどんへの愛が尋常ではない」ことに気づいた古田さんは、うどん作りを楽しめる「英才教育キット」を開発。
1セット7,000円で販売したところ、孫と一緒にうどんづくりを体験したい祖父母層を中心に購入され、ヒット商品となった。「10玉分の原価で7,000円。香川県内のおじいちゃんおばあちゃんは、うどんではなく孫との時間にお金を払っているわけです」(古田さん)。

「大切なことは、次の流行りを探すことでも、既存のものに反対をすることでも、体制に依存することでもなく、新しい時代の価値を生み出していくことです」と締めくくった古田さんのプレゼンテーションに、参加者から熱い拍手が沸き起こった。