日本の人口減少が進み、近い将来、日常の交通手段や燃料供給、教育機関など、今は当たり前にあるものがなくなってしまう「変化」が次々と起こる可能性があります。その時、私たちは自分の心をどのように対応させれば良いのでしょうか。リトケイの新著『世界をかえるシマ思考 -離島に学ぶ、生きるすべ』より、人口減という変化を可能性に変えるヒントを紹介します。
>>記事前編はこちら
※この記事は『季刊ritokei』45号(2024年4月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。
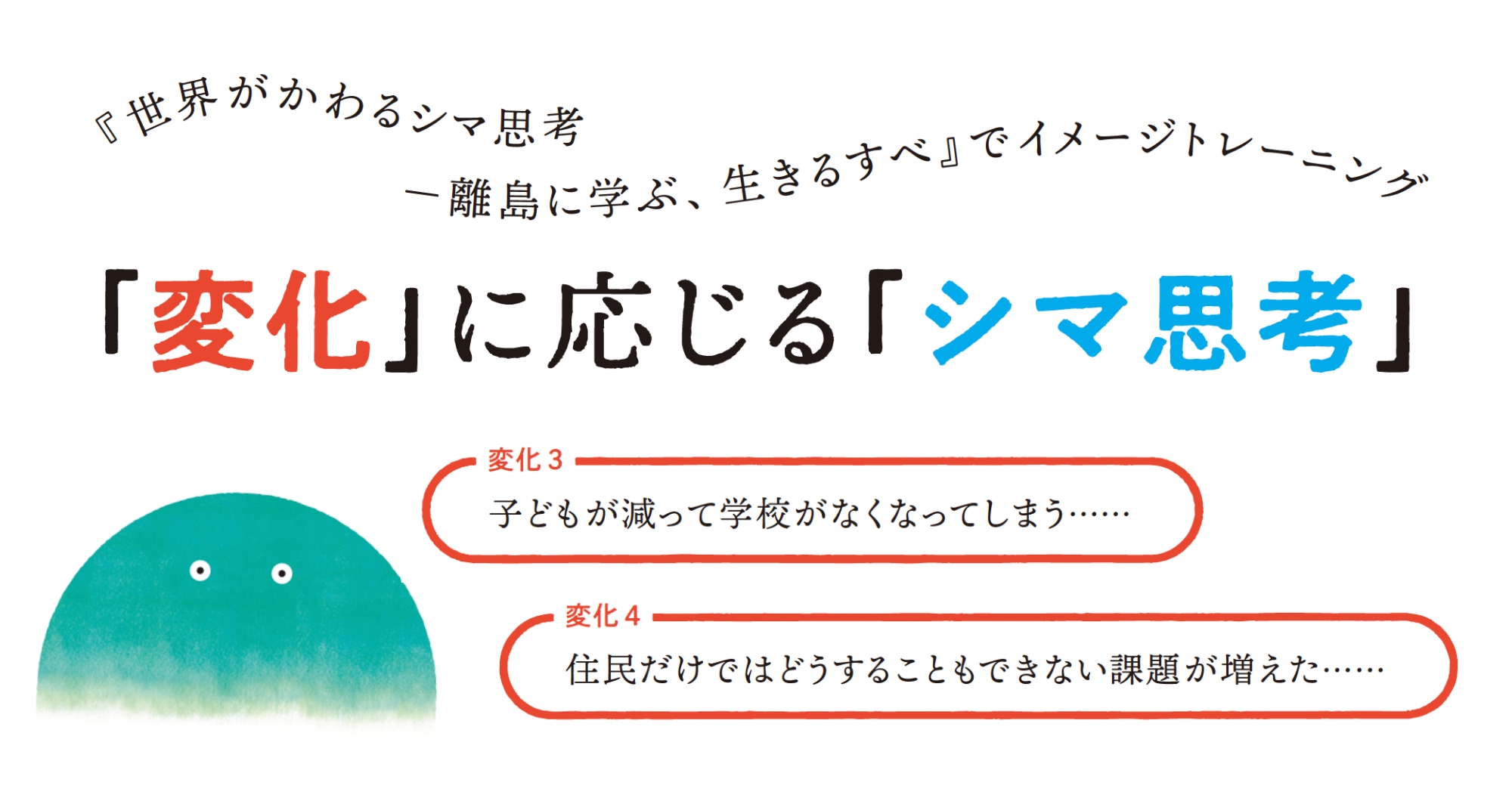
学校の存続危機や地域の支え合いでは解決できない問題、どう対応する?
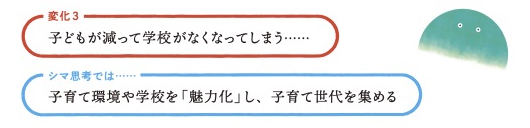
子どもがあふれかえっていた時代が過去のものとなった日本では、学校を維持することも簡単ではありません。過疎地域の公立学校では財政難も重なり、学校の統廃合や閉校が続々と増えています。
地域から保育園や学校が消えてしまうと、その地域を巣立った子どもが子育て世代になった時に、帰りたくても帰れない地域になってしまいます。子育て教育環境を守ることは、住み続けたいふるさとがある人にとっての最重要課題です。
子どもの減少が著しかった離島地域では、1970年代から離島留学制度を取り入れ地域外の子や親を受け入れてきました。この制度は、地域の存続を左右する重要施策である一方、豊かな自然や人々の支え合いが少ない地域で育つ子や親にとっても貴重な制度です。
参考記事>>島の学校で学ぼう!令和6年度「離島留学」募集情報まとめ(随時更新)
近年では「不便」が残る地域ほど「生きる力」や「非認知的能力」を育みやすいとして、離島やへき地を選ぶ子育て層も増えています。
 「学校魅力化」発祥の地、海士町にある魅力的な公営塾 「隠岐國学習センター」
「学校魅力化」発祥の地、海士町にある魅力的な公営塾 「隠岐國学習センター」
また、少子化により高校存続の危機が訪れた隠岐諸島の島根県立隠岐島前高校(中ノ島)では、「学校存続のための活動」を「学校魅力化」と言い換え、子どもたちの夢を支える「夢ゼミ」や「公営塾」などさまざまな教育コンテンツを発明。
島の高校から有名大学に進学する生徒も現れ、生徒数はV字回復。この島の運命を変えたイノベーションはその後、「地域・教育魅力化プラットフォーム」と名を変え全国各地へと波及しました。
学校の存続には「魅力化」で応じる。そうするうちに子育て層が集まり、人口が維持できると、島内外をつなぐ航路をはじめ、さまざまなインフラの維持が叶う。未来をかえる発展にも期待ができるシマ思考です。
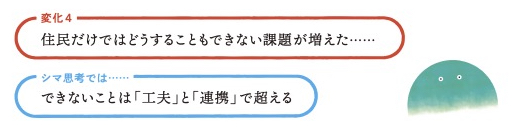
離島や山間部など、隣町から離れた地域で人口が減ると、住民同士の支え合いだけではどうすることもできない課題が増えていきます。
例えば、海洋ごみ。世界中から流れ着く漂着ごみは過去半世紀のうちに爆発的に増え、今や毎日のように沿岸地域に押し寄せています。その量は、地域内から出るごみの何十倍、何百倍ともなり、住民だけで片付けることは不可能。そこで重要になるのが「連携」です。
山形県の飛島は人口約100人台の小さな島。かつては最大2メートルの高さまで漂着ごみが堆積していた島では、数百人規模のボランティアを地域外から受け入れ、清掃活動を続けています。
その連携は海洋ごみ問題だけにとどまらず、近年は島を舞台に産官学民の多様な関係人口を対象に、小さな島だけでは叶わないアイデアを考え、実現する「合宿」を実行。海洋ごみを運ぶ「運搬ロボット」や、ドローンでカレーを配達する「空飛ぶカレープロジェクト」など、ユニークな取り組みが生まれています。
 新たな方法を取り入れ島の課題を超える座間味村 (©OCVB)
新たな方法を取り入れ島の課題を超える座間味村 (©OCVB)
また、沖縄の座間味村(座間味島、阿嘉島、慶留間島)では、物価高や財政難、人手不足により難易度があがっている公共インフラの整備に、PPP(※)やリース方式で庁舎の新築を実現。島の住居問題に対し、行政が所有する土地を活用して民間アパートを立てる官民共同アパートの建築など、前例のない仕組みも積極的に取り入れています。
※Public Private Partnership。公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うこと
立ちはだかる壁に向かって「わからない」「前例がない」と立ち止まるのではなく、「どうやったらできるか?」と思考をめぐらせ、自分たちだけでは叶わないことは工夫と連携で超える。これからの社会変化に対応するための重要なシマ思考です。