徳之島(とくのしま)、沖永良部島(おきのえらぶじま)、与論島(よろんじま)。鹿児島から沖縄へと続く、8つの有人島からなる奄美群島の中で、最も南にあるのが「奄美群島南三島」です。
この南三島から日々、島のハッピーニュースを発信しているのが「奄美群島南三島経済新聞(通称・みなさん新聞)」。8月23日の日曜日、リトケイとみなさん新聞のコラボ企画「シマビト大学@沖永良部島」に参加し、その前後で徳之島・与論島もめぐりました。
プロフィール:
卜部奏音(うらべ・かなね)。取材・インタビューライター。酒匠・唎酒師(ききざけし)の資格を持ち、新潟への移住を機に日本酒蔵の取材記事執筆を始める。好きな島は北海道・利尻島。
唎酒師ライター、黒糖焼酎蔵を巡る
私は普段、唎酒師ライターとして、新潟を拠点に日本酒蔵の取材記事を書く仕事をしています。島ならではの自然や文化、そして人々の温かさが感じられる離島旅が好きなこと、そして島での取材を体験できることに惹かれて今回の企画に申し込みました。
この旅で特に楽しみにしていたのが「焼酎蔵見学」。私の中で奄美と言えば、なんといっても黒糖焼酎です。奄美群島でしか造られていない焼酎で、黒糖のやさしい甘い香りと、クセのないすっきりした飲み口が魅力です。
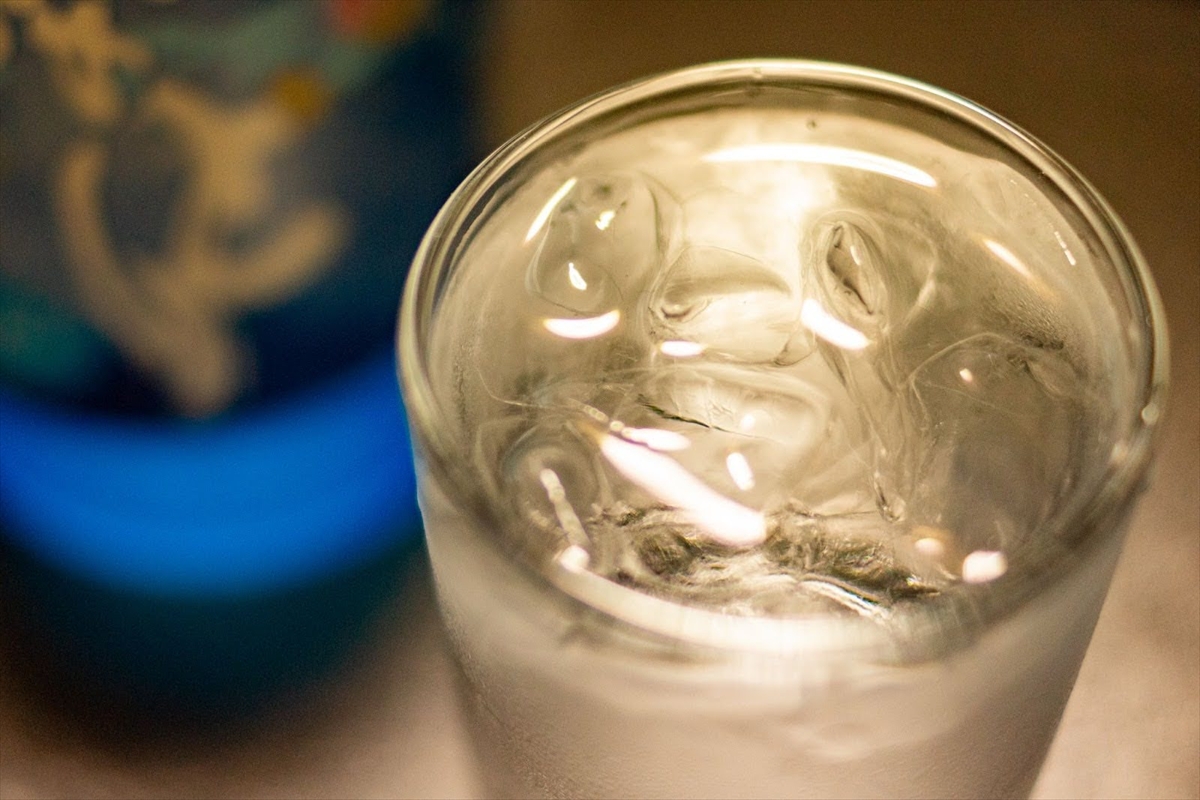
仕事で日本酒蔵はいくつも訪れているのですが、焼酎蔵は初めて。以前、焼酎唎酒師の資格を取ったこともあり焼酎を飲むのは好きだったのですが、どんな環境で造られているのかは見たことがありませんでした。
南三島には徳之島に7つ、沖永良部島に6つ、与論島に1つの計14の焼酎蔵があります。今回はみなさん新聞の記者の皆さんの案内で「奄美大島にしかわ酒造(徳之島)」「新納酒造(沖永良部島)」「有村酒造(与論島)」の3つの黒糖焼酎蔵をめぐることができました。
そこで感じたのは、決してひとくくりにはできない、黒糖焼酎の個性とそれを育む島々の個性。見学の様子をまじえながら、三島の旅をふり返ります。
 沖永良部島の笠石海浜公園の展望台から望む
沖永良部島の笠石海浜公園の展望台から望む
1000石を超える大工場が生んだ“革命児”
奄美大島にしかわ酒造(徳之島)
まず初めに訪れたのは、みなさん新聞徳之島支局の松岡さんに酒蔵見学を予約いただいた、「奄美大島にしかわ酒造」。港近くでレンタルした原付で20分ほど山道を走ると、突然、大きな黒い建物が現れました。建物の外からもわかるほど、蒸した米やつきたての餅のような甘い香りが漂っています。

中に入ると、先ほどの米の香りとはがらりと変わって、香ばしい黒糖の香りに包まれました。シマビト大学の参加者で徳之島在住経験のある方が「観光客向けに『魅せる』ことも重視した酒蔵」と言う通り、酒造場の2階には製造の工程をわかりやすく解説したパネル展示があり、ガラス越しに造りの様子を見学できました。
2019年の竣工式の地元紙の記事では、西川社長が「世界自然遺産に向けた取り組みの声にも応えて観光コースを設け、皆さまが集える場所として工場見学、噴水公園なども設置した」と話しており、南三島で唯一世界遺産エリアを擁する徳之島の特色が感じられます。
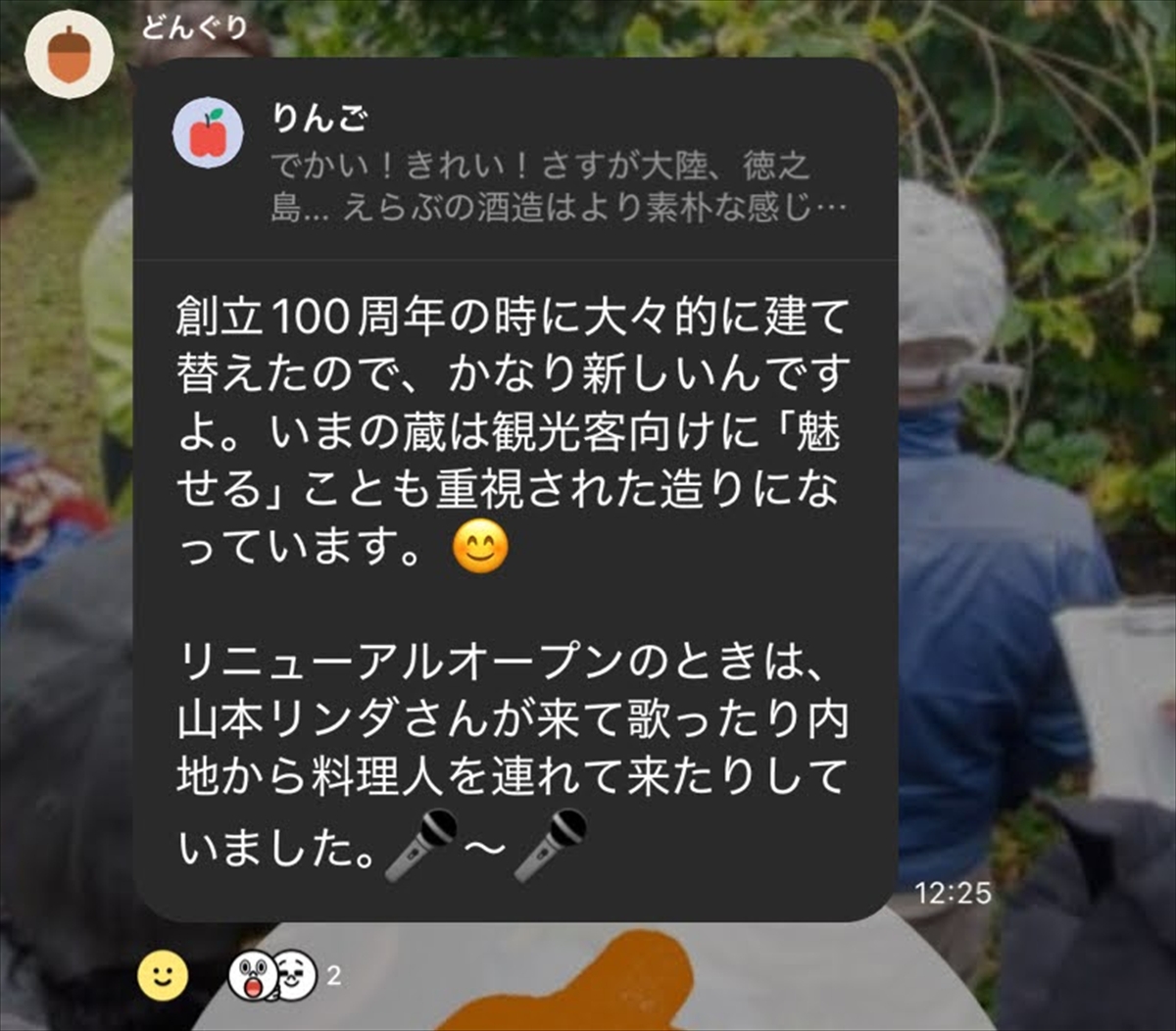 シマビト大学では、グループLINEを使って島の情報交換をしていました。参加者には南三島在住の方も多く、LINEでは島のおすすめ情報が日々飛び交っていました。
シマビト大学では、グループLINEを使って島の情報交換をしていました。参加者には南三島在住の方も多く、LINEでは島のおすすめ情報が日々飛び交っていました。
奄美大島にしかわ酒造の特徴は、1000石(※)を超える生産量を支える、大型で近代的な設備。米を洗い、水を吸わせ、蒸し、麹菌(こうじきん)を繁殖させて米麹を作る——その一連の工程をすべて一つの機械で行えるそうです。日本酒蔵では、米を洗う機械、蒸す機械、米麹を作る機械、と分かれているところが多いため、その違いに驚きました。

最後に商品ラインアップの説明を聞き、見学を終えました。代表銘柄「島のナポレオン」は、“黒糖焼酎に革命を起こすようなお酒になってほしい”という願いを込めて名付けられたそう。見学の最後にあった飲み方の紹介パネルでは、パインジュースやアイスBOX、そしてコーラやコーヒーまで(!)まさに革命的な割り方が提案されていて、そんな飲み方があるのか…とびっくりしました。

※「石(こく)」はお酒の体積を表す単位で、1000石は約18万リットルにあたる
戦災、台風、火事…苦難の歴史の上で
新納酒造(沖永良部島)
次に訪れたのは沖永良部島の「新納(にいろ)酒造」。島の西側、海沿いからサトウキビ畑の続く坂を登ると、蔵が姿を現します。
11〜3月の間に行われる造りは終わっていましたが、酒造場の中を案内していただきました。説明を聞きながら気になったのは、建物の壁やタンクのところどころに付いている、黒いスス。なんとこの新納酒造、2017年に火災に遭い酒造場の隣の倉庫が消失。酒造場にも延焼しましたが消火が早かったため、中の機械は無事で済んだそうです。
歴史をさかのぼると、1945年にも、空襲によって当時の酒造場が全焼。必死の想いで再建したものの、当時は海の近くにあったため1977年の沖永良部台風で大きな被害を受け、現在の場所への移転を余儀なくされたそうです。こうした苦難の歴史を乗り越えたうえに今の焼酎造りがあることを思うと、頭が下がる想いでした。
みなさん新聞沖永良部支局のネルソン水嶋さんによると、「新納酒造」の特徴は、「暗川(くらごう)」の水だそう。沖永良部島は珊瑚礁が隆起した島で、多くの水源が地表ではなく地下にあり、それらは暗川(くらごう)と呼ばれます。新納酒造は田皆字(たみなあざ)の暗川のそばにあり、そこから水を引いて蒸留後の冷却水として使っているそうです。こうした珊瑚礁の島ならではの水源を活用している点で、とても沖永良部島らしい焼酎蔵だと感じました。

見学の最後には、焼酎の試飲タイム。減圧蒸留であっさり軽やかな味わいの「をちみず」や、5年以上熟成させたどっしりと深みのある「水連洞」、黒糖ブロックを直接入れる新製法で造られ、甘く華やかな香りが際立つ「天下無双」など、黒糖焼酎の持つ豊かな広がりを感じられた時間でした。

与論献奉を支える“あえて”の20度
有村酒造(与論島)
周囲23kmと、南三島の中で最も小さい与論島。島唯一の焼酎蔵、「有村酒造」はスーパーや飲食店が集まる中心地・茶花の街中にありました。
1階と2階にわかれた酒造場の中を案内してもらう中で、前日にスーパーで有村酒造の「島有泉」を買ったときから気になっていた疑問を聞いてみました。それは、アルコール度数が20度であること。焼酎の度数は25度が一般的で、「度数が高い方が割って多く飲めるため、コスパがいい」という理由から、30度の商品を出している蔵もあります。なぜ、有村酒造は少し低めにしているのでしょうか?
その理由は、与論島の伝統的なおもてなし「与論献奉(よろんけんぽう)」にありました。与論献奉では、盃に注がれた黒糖焼酎を回し飲みしながら自己紹介や歓迎のメッセージを述べます。島の居酒屋で与論献奉が始まると、ほかのテーブルからも飛び入り参加し、何周も盃が回り続ける…なんてこともあるそうです。

みなさん新聞与論支局の江藤さんから提供いただいた与論献奉の風景。こちらはお母様が来島されたときに友人の家で撮られた写真だそうで、与論献奉について「島外からやってきた人を歓迎するために行っていたそうです。酒の出来具合を確認するために施工主が毒味(味見)をしてから客に振る舞っていたことがルーツだと言われています」とのことです。
案内してくれた有村酒造の有村さんいわく、「与論献奉をするときに、酔いつぶれずに少しでも長くその時間を楽しめるように、あえて低めのアルコール度数にしているんです」とのこと。私も宿で与論献奉を体験しましたが、同じ盃のお酒を飲んで自己紹介することで、初対面でも一気に距離が近づく感じがして気持ちがほぐれました。度数の裏には、そんな楽しい時間を支える工夫が隠されていたことを知って、ますます心が温かくなりました。

度数以外に特徴的なのは、「甕(かめ)仕込み」。焼酎造りでは通常、ステンレスやホーローの大きなタンクに米麹と黒糖を入れて発酵させますが、有村酒造では創業当時から50年以上、甕を使っています。甕はタンクに比べると容量が小さく、当初は発酵中に出る泡があふれる苦労もあったそうですが、昔ながらのやり方を丁寧に守り続けているそうです。

ひとくくりにできない南三島と黒糖焼酎
シマビト大学を機に、南三島とその黒糖焼酎蔵をめぐる中で、これまでぼんやりと“奄美の島々”としか認識できていなかった各島の輪郭が、はっきりするような感覚がありました。
例えば、南三島の中でいちばん北にある徳之島は「ダイナミックでエネルギーあふれる島」。三島の中で一番高い山があり、その標高は沖永良部島の約2.7倍。その周りには深い森が広がるため、人が簡単には立ち入れないミステリアスな世界が残されているように感じます。山を中心に広がる島中に、アマミノクロウサギやリュウキュウイノシシ、闘牛文化など、活発でエネルギーある生きものや文化があふれている印象がありました。

反対に、いちばん南の与論島はなだらかな地形で見晴らしがよく、「明るくひらけた島」の雰囲気を感じました。海の色も青いというより、まるでガラス細工のような明るく透明度の高い水色で、他のどこにもない色合いです。小さいため道行く人やすれちがう車の中にしょっちゅう知り合いがいる、人と人の距離が近い島のように感じました。

そして、そのふたつにはさまれた沖永良部島は、「自然に根差した生活の島」という印象がありました。生活用水になっていた川がいくつも地下に流れ、サトウキビ畑の隣の林に突然古いお墓が現れ、毎月開かれる市では漁師さんが獲れたての魚を売り、通りすがりの旅人も交えて宴会する…暮らしの中に、自然と人とのつながりが色濃く織り込まれているようでした。

今回の旅を通して、これまで「黒糖焼酎」「奄美の島々」とざっくりとひとくくりにしてしまっていたものの中にあった、それぞれの個性と多様性の豊かさを、肌で感じることができたのが大きな収穫でした。
そして何より一番嬉しかったのは、みなさん新聞の皆さんとシマビト大学の参加者との繋がりから、「また遊びに来ます」と言える人が島に何人もできたこと。この繋がりが関係人口の初めの一歩なのかもしれない、と感じた旅でした。