心に浮かぶ疑問や地域課題を「対話」から紐解く。新潟大学佐渡自然共生科学センター教授・豊田光世さんは、自らの問いを深めるうちにハワイで「p4c(子どもの哲学)」 と出会い、日本に持ち帰った。学校や地域づくりの現場でも活用されるp4c(※)について聞いた。
※p4c (Philosophy for Children)……子どもたちが円座になり問いを出し合いながら対話を通じて思考を深めていく教育手法。単に知識を獲得するのではなく、自ら問いを立て、仲間と意見を交わし、異なる視点を重ね合わせることで、新たな見方・考え方を獲得することを目指す。学校現場のみならず「Philosophy for Community」の意味で地域コミュニティや企業研修の場にも広がっている
※この記事は『季刊ritokei』49号(2025年5月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の公式設置ポイントにてご覧いただけます。
佐渡島/新潟
新潟県沖に浮かぶ佐渡島は、面積約855キロ平方メートル、人口約4.7万人の日本最大級の離島。豊かな自然と歴史文化を併せ持ち、トキの野生復帰の島としても知られる。新潟港から高速船で約1時間、フェリーで約2時間半でアクセスできる
安全に対話できるp4cで共有される多様な意見
p4cを日本に広める豊田光世さんは佐渡在住。環境間題への関心から分子生物学を学び、テキサスで環境倫理学を研究。その際、「環境にやさしい思想や考え方を、どうすれば多くの人に伝えられるか?」という問いにぶつかり、哲学や価値観の重要性に大かれてハワイ大学に移りp4c(Philosophy for Communiry)に出会った。
「子どもの哲学」と直訳されるp4cを履修した豊田さんは、それまでの考えを根本からゆさぶられた。「どうすれば伝えられるか?」という間いも「 思想の植え付けにすぎないかもしれない」と感じたのだ。
「本当に必要なことは、いろんな人が膝をつきあわせて考えを共有する場をつくることではないかと思ったんです」。対話の場では、替同できる意見と、賛同できない意見があがってくる。p4cはそこで、一度立ち止まって「この人はそんな風に考えるんだ」と考えることを促す。
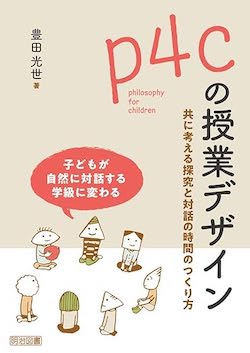 豊田さんの著書 『p4c の授業デザイン- 共に考える探求と対話の時間のつくり方』 (明治図書出版)
豊田さんの著書 『p4c の授業デザイン- 共に考える探求と対話の時間のつくり方』 (明治図書出版)
「30人の参加者がいたら30通りの見方が共有されることで、自分ひとりでは得られなかった到達点にたどりつけるんです」。p4cはあくまで対話手法。合意形成が目的ではないが、p4cによって共有される多様な意見は、合意を形成するための「素材」になる。
p4cにはいくつかの具体的ルールがある。そのひとつがコミュニティーボールとして使われる「 毛糸玉」だ。車座になった参加者はまず毛糸をぐるぐると巻き、毛糸玉をつくる。その毛糸玉を手にした人がその瞬間の発言者となることで、自発的な発言が難しい参加者も安心して声を発することができる。
ネイティブアメリカンが使う「トーキングスティック」のような存在が、誰もが安心して発言できる「セーフティ(安全)」な場をつくる。
 p4cで使われる毛糸玉
p4cで使われる毛糸玉
Childrenの哲学はCommunityの哲学に
安心して発言できる場には自身の思い入れもある。東京で生まれ育った子ども時代 「教室で手をあげて発言することもできなかった」と豊田さん。そんな経験も活かしながら普及するp4cは、ChildrenからCommunityへと広がっている。
ある集落でワークショップを担当した時のこと、主催者が「この地域に問題はない」と話すなか、参加していた女性が「満足なんかしてませんよ。我慢してるんです」と口火を切ったことから、まわりの女性から次々に「買い物の足がない」「かつて聞こえていた盆の鐘の音が消えて寂しい」という本音が飛び出したことがあった。
 母校・ハワイ大学にて。左が豊田さん
母校・ハワイ大学にて。左が豊田さん
「公の場で常に発言する人はなんとなく決まっていることが多いですが、『私には何も意見はありません』と感じていた人でも、安心して語れる場があることで、 自分の内にある思いや考えに気づき、他者の新たな視点を引き出すきっかけにもなるのです」。
未来の理想を描き、現在の行動を決定する「バックキャスティング」が地域づくりの現場で求められることが増えたが、「離島や中山間地域には未来が描けなくて困っている人がいる。『10年後にどんな未来をつくりたいですか?』なんて最初から話せないので、どんなことでもいいから、地域のことや心に浮かんだことを話してもらえますか?と少しずつ語り出してもらっています」と豊田さんは語る。
「めんどくさい」を「おもしろい」 にかえる
とはいえ根気がいる。ある集落では、住民が「棚田をどうしていきたいか」を語る場で、3回目の対話機会になってようやく「こうしたい」という想いが共有され始めた。ところが、それを聞いた若手住民が「くだらねえ」「誰がやるのか」と憤慨し、その場を後にした。
 p4c対話の様子。対話と想いを文字にすることも重要なポイント
p4c対話の様子。対話と想いを文字にすることも重要なポイント
それでも粘り強く場を設定しなおし、「やってみたいことから始めて、一歩進んだらまた考えてみませんか?」という対話を続けるうちに、小さな行動と成功体験が生まれ、対話を拒絶していた若手も、いつしか地域づくりを担う中核メンバーに変わっていった。
「めんどくさい意見が出たときに『めんどくさい』と思ったら何も生み出せなくなります。想定した状況を逸脱する反応を 『おもしろい』と思えるかがポイント」。
それは、寝た子を起こすことでもある。「例えば、対立がある時には、異なる視点があぶりだされていかなければならないと思うんです。対立を見えないようにして平和を保つこともできますが、 本当に前に進もうという時は、違う考えを持っている人との対話も必要なんです」。
お互いの腹のうちを共有する究極の対話により、「めんどくさい」が「おもしろい」に変われば、人間社会はよりしなやかさを増していくだろう。