新潟・佐渡島の子育て環境モニターツアー(後編):地元の買い物体験と文化祭参加
- 投稿日
佐渡島(さどがしま|新潟県)は日本海側最大の離島で、島の面積は約855平方キロメートル、島内に約55,000人が暮らしています。教育の場としては小学校...


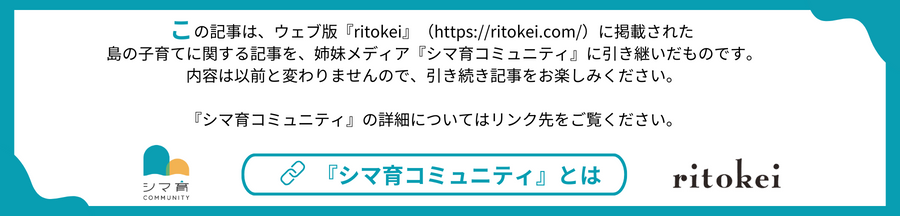
奄美大島(あまみおおしま|鹿児島県)南部に位置し、奄美大島の南西部と加計呂麻島(かけろまじま|鹿児島県)、与路島(よろしま|鹿児島県)、請島(うけしま|鹿児島県)からなる瀬戸内町には、約9,000人の人々が暮らしています。
西阿室(にしあむろ)のテンテン踊り、諸鈍(しょどん)シバヤ、油井(ゆい)の豊年踊りなど、神事にまつわる行事が身近で、これらの年中行事や伝統芸能は今も太陰暦で行われています。亜熱帯の自然が豊かであり、国の特別天然記念物であるアマミノクロウサギや、アマミトゲネズミ、アマミエビネなど固有の動植物も多い地域です。
今回は、加計呂麻島の西阿室小学校校長の猿渡有一先生と、親子型の留学を体験して6年目になるお母さんの新山麻夢さんにお話をうかがいました。

瀬戸内町立西阿室小学校校長
猿渡有一先生
学校のある西阿室地区は、一集落に一つの学校がある地域で約50世帯、100名弱が暮らす、お互いが家族のような地域です。現在の全校児童数は9名、そのうち5名が留学生です。
サンゴ礁でのシュノーケリングなど海洋体験、テンテン踊り(※1)、立神太鼓(※2)、三味線の演奏などといった郷土芸能や、パッションフルーツの収穫などが体験できるのはこの地域ならでは。
※1 旧暦の8月15日、西阿室集落の豊年祭で踊られる
※2 西阿室小学校の元教員により作られ、古くから信仰の対象である西阿室の沖の小島・立神から名付けられた。波が立神に突き当たる様子を太鼓で表現しており、奄美の踊りも取り入れている


行事がなくても、地域の方々は学校に自由に出入りしています。自宅で育てたバナナを「たくさんできたから」と届けてくれたり、校庭で児童が一輪車の練習をしていれば応援してくれたり。地域の方々の存在が児童たちの励みにもなっています。
様々な世代との交流を通し成長する子どもたち
児童数が少ないため、毎日の学校生活の中で一人ひとりが役割を持ち、責任を果たさなければ何事も進まないため、自分の意見も積極的に発言できるようになります。
児童たちは違う学年や地域のさまざまな年代の方と交流し、お互いに協力し合う環境で生活をしていますが、このような経験は、将来社会に出た時に役に立つと思っています。
離島にとって、学校が存続することはとても重要なので、1年でも留学を体験していただけたらうれしいです。


6年前に加計呂麻島・西阿室集落に移住
新山麻夢さん
島で生活を始め、子どもたちが学校に通うようになり6年目になります。長女は中学2年生、次女も小学校6年生になり、一昨年には三女が誕生し、現在も妊娠中と……この島で家族も増えました。
仕事面などでは東京のようにはいかないこともありますが、島ではお金で変えられないものをたくさん得ています。

島に来る前は東京で生活し、シングルマザーとして仕事と長女、次女の子育てに必死でした。公私ともに充実はしていましたが、自宅にほとんどいられないほど多忙で、こんな状態の育児が正しいのか?と疑問を感じていた時、加計呂麻島での留学制度を知り、まずは8月に1か月体験留学をしました。
8月の加計呂麻島はさまざまな行事で年間で一番忙しく、のんびりと過ごすというより忙しい中に身を任せる毎日でしたが、そんな時期でも地域の皆さんは私たち親子を受け入れてくれました。子どもたちは島で水を得た魚のように元気になり「帰りたくない」「もっとお母さんと一緒にいたい!」と言われて、もう一回、自分と子どもたちとの向き合い方や人生を考え直す決断の時だなと感じ、移住を決意しました。
子どもも親も安心して過ごせる環境で家族の絆が深まる
島の運動会や学習発表会などでは、子どもの家族だけでなく地域の方が大勢参加するので都会では味わえない賑やかさがあります。
地域の方が子どもに「歌を頑張ってたね」「一輪車乗れてよかったね」と普段から何気ない言葉をかけてくれたり、いけないことをすれば叱ってくれたりと、地域全体で子育てをしてもらうことで、子どもも親も安心して過ごせています。
子どもたちは島に来てから、褒められてうれしかったことやできるようになったことなどが増え、私にも報告してくれるようになりました。

子どもの数が少ないためか、大人が介入しなくても、子ども同士で喧嘩後に仲直りしたり、慰めたり、都会ではなかった子ども同士の人間関係がきちんとできあがっています。年齢も違う子ども同士が自分と他人との違いを認め合い、自分さえよければいいという考えではなく、苦手なことをしている子がいればケアをしています。
島暮らしでは習い事ができないなど、選択肢が狭まることもあります。大人は草刈りなど地域の仕事や祭りなどの行事で忙しく、人と関わらずに生きることはできません。一人になりたい時は島を出なくてはいけないほど。でも、誰かが困っていたら手助けするのは当然だと思います。
移住後、色々と失敗や、辛いこともありましたが、再婚した夫に「俺だけは味方だ」「子どもが幸せならいいじゃないか」と励まされ、自分が自分らしくいられればいいんだと開き直ったら楽になりました。
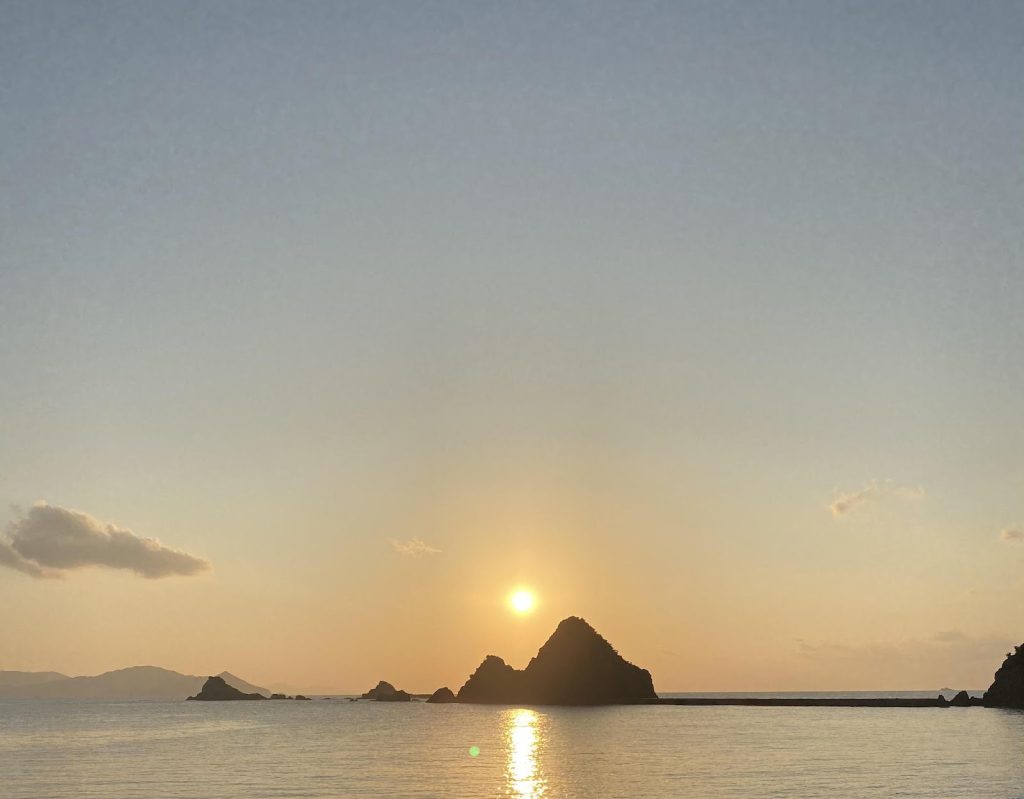
まずは気負わずに島暮らしを体験してほしい
これから留学をするお子さんやご家族へは、体験留学をしたら必ず移住しなきゃいけないと考えたり、まだ起こっていないことで悩んだりしなくても大丈夫!と伝えたいです。
学校の先生方や西阿室の区長さんはじめ、集落全体が移住者に対して優しいので、仕事や家、学校のことなど、分からないことは相談にのってくれます。
私も島での子育ての良さをともに体験してほしいという思いから、「体験移住ハウス」を立ち上げたところ、3組の移住が決まり、地域の子どもが一気に7人増えて賑やかになりました。
「一生の選択だから」などと考えず、まずは気負わず気楽に、島での生活や空気感、子どもが感じ取ることを受け止めて、体験してほしいです。その上で移住したいとなったら、私たちができる限りのサポートをします。
〈瀬戸内町の「にほんの里加計呂麻留学」概要〉【受入学校名】古仁屋小学校・古仁屋中学校・阿木名小中学校を除く瀬戸内町内の各小・中学校
【対象】全国:小学1年生〜中学3年生
【受入体制】親子型(親子で島に移住して通学)
【留学期間】移住後、中学卒業まで
【募集時期】随時
【詳細URL】http://www.town.setouchi.lg.jp/k-soumu/kan/iju/jutaku/ryugaku/ryugaku.html
【問合せ先】瀬戸内町教育委員会 0997-72-0113
* * *
「シマ育成コミュニティの記事更新」「シマ育勉強会の告知」「モニターツアーの告知」などの情報をLINEでお届け!LINE公式アカウントにご登録いただくことで、見逃すことはありません。

『シマ育コミュニティ』を運営する『NPO法人離島経済新聞社(リトケイ)』は、よりたくさんの親子が、魅力あふれるシマ育環境に出会い、明るい未来を歩んでいけるよう、『シマ育応援団』としてリトケイをご支援いただける個人・法人を募集しています。
>>シマ育応援団になる(リトケイと日本の離島を応援する|リトケイ)

リトケイは、416島ある有人離島の「島の宝を未来につなぐこと」をミッションに、シマ育コミュニティ運営のほか、メディア事業、魚食文化の継承、環境保全活動の支援など多分野に渡り活動しています。メールマガジン『リトケイ通信』では月に2回、リトケイの情報発信やお知らせについてお届けしております。配信を希望される方は以下のフォームよりお申し込みください。
>>リトケイを知る(1ページで分かる離島経済新聞社|リトケイ)
>>メールマガジンに登録する(『リトケイ通信』お申し込みフォーム)