シマ育のしくみ:島根県・海士町(中ノ島)の小中学校・高校留学
- 投稿日
「海士町(中ノ島)」のシマ育の概要 海士町(あまちょう|島根県)は、島根県の北方、日本海に浮かぶ隠岐諸島のひとつ、中ノ島を主島とする町です。かつては少...


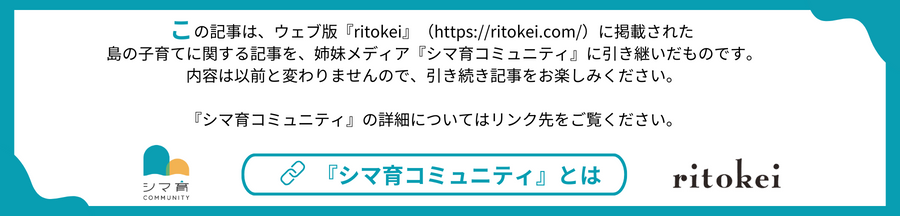
鹿児島県が推進する山村留学制度では、離島を有する県内13自治体も同制度を活用している。2017年度は九州本土と離島地域の導入地域で、全国各地から160人の小中学生を受け入れた。ここでは奄美大島(あまみおおしま)南部の瀬戸内町(せとうちちょう)の事例を紹介する。
(記事中編はこちら)
※この記事は、『季刊ritokei』24号(2018年5月下旬発行)「島と親子に離島留学という可能性を」特集連動記事です。
文・竹内松裕

加計呂麻島(かけろまじま)は2009年、朝日新聞社と森林文化協会による「にほんの里100選」に選出された。瀬戸内町が2012年から加計呂麻島と請島(うけしま)、与路島(よろしま)で実施する留学制度「にほんの里 加計呂麻留学」の名称は、このことに由来する。
小学校1年~中学3年までを対象とする加計呂麻留学の特長のひとつは、学校存続に加え島の人口増を図るため、家族留学のみに絞っている点だ。2018年度は新しく2人を受け入れ、昨年度以前からの継続を含め22人が留学生として加計呂麻島で暮らしている。
加計呂麻島の中央部に位置する秋徳(あきとく)中学校では2018年度、留学生4人と島出身の生徒1人が通う。

同校の吉永教頭によると留学に至った経緯はさまざまで、親や祖父母が秋徳地域出身で島に戻ってきた家族や、自然豊かな環境に惹かれ移住した家族がいるという。
「地域社会で中核を担う30~40歳代が来たことは活性化につながりますし、生徒が増えることは学校存続につながる。卒業生にとっても、母校の存続を意義のあることとして喜びを感じてくれているのではないでしょうか」(吉永教頭)
生徒たちは小規模学級で和気あいあいと学ぶ。1年経つと「これまでは周囲に埋もれて自己表現が苦手だった子どもが、明るく活発に自己表現をするようになった」「険しかった表情が和らぎ、刺々しい口調がなくなった」と保護者の喜びの声が学校に届く。吉永教頭は「生徒一人ひとりの多様性を認め合うことを学びのベースにしています」と話す。
加計呂麻留学では、ルーツをたどり島に移り住んだ家族がいることがわかる。留学生は高校進学などで島外に出ても、折に触れて島に戻る。同校はその際には遊び場となり、かつての生徒たちを何度でも迎え入れる。
鹿児島県教育委員会の担当者は、山村留学が地域活性化に果たす役割は大きいと受け止めている。
「県や各市町村の広報活動に加えて、留学希望者に助成金を準備するなど制度面でサポートがあり、さらに南北600kmに伸びる本県のスケールの大きな自然と温暖な気候、独特な文化に触れられる体験活動、地域の方々との交流活動が実を結んでいます」と話している。
<出版物に関するお詫びと訂正>
NPO法人離島経済新聞社より2018年5月下旬に発行いたしました 『季刊ritokei(リトケイ)』24号において表記に誤りがありました。読者の皆さまならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことを お詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。
正しくは以下の通りです。
▼P8 写真キャプション表記
【誤】瀬戸内町の「にほんの里加計呂麻留学」でシーカヤックを楽しむ子どもたち
【正】瀬戸内町の「にほんの里加計呂麻留学」で船こぎを楽しむ子どもたち
* * *
「シマ育成コミュニティの記事更新」「シマ育勉強会の告知」「モニターツアーの告知」などの情報をLINEでお届け!LINE公式アカウントにご登録いただくことで、見逃すことはありません。

『シマ育コミュニティ』を運営する『NPO法人離島経済新聞社(リトケイ)』は、よりたくさんの親子が、魅力あふれるシマ育環境に出会い、明るい未来を歩んでいけるよう、『シマ育応援団』としてリトケイをご支援いただける個人・法人を募集しています。
>>シマ育応援団になる(リトケイと日本の離島を応援する|リトケイ)

リトケイは、416島ある有人離島の「島の宝を未来につなぐこと」をミッションに、シマ育コミュニティ運営のほか、メディア事業、魚食文化の継承、環境保全活動の支援など多分野に渡り活動しています。メールマガジン『リトケイ通信』では月に2回、リトケイの情報発信やお知らせについてお届けしております。配信を希望される方は以下のフォームよりお申し込みください。
>>リトケイを知る(1ページで分かる離島経済新聞社|リトケイ)
>>メールマガジンに登録する(『リトケイ通信』お申し込みフォーム)